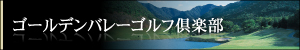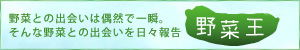今週の週刊文春に中嶋常幸プロが、ティーチングプロの役割についてコメントしています。三平も、いつか誰かがこういうコメントをするんだろうなあ?待ちに待っていたコメントでした。日本人というとシャイな性格もあってか、人にゴルフを教わる、ということをあまりしたがらない傾向があります。それで世の中自己流で覚えました、というオジサンゴルファーがなんと多いことか。
米国のレッスン事情はちょっと違います。ゴルフ誌には、年間ティーチングプロランキングが出るほど、ティーチングプロの存在が認められています。
あのジャック・二クラウスもジャック・グラウトというティーチングプロが密着していましたし、トム・ワトソンもバイロン・ネルソンという名伯楽がついていました。近年ではタイガー・ウッズもブッチ・ハーモン、ハンク・ヘイニーと米国を代表するティーチングプロが見ていました。フィル・ミケルソンもジュニアのころは、ディーン・ラインマスから徹底してアプローチ、パットを教え込まれています。彼の天下一品のロブショットは、このラインマス仕込みです。
三平が最初に、ティーチングプロの存在を目の当たりにしたのは、かれこれ17,8年前のことでしょうか?ジャマイカで開催された世界ゴルフ選手権に行った時のことです。あの日本でも有名になったデヴィット・レッドベターが、J・V・シンとニック・ファルドの間を言ったり来たりして、ずうーと教えていた姿を見た時です。身体の調子、精神的にも日々違うスイングになる、だからいつも見てもらって修整している、とコメントしていました。こんな世界のトッププロでもこうして絶えず見てもらうんだな、と衝撃を受けたことを覚えています。
先日日本のシニアの大御所と言われている人も、石川遼に米国のいいティーチングプロがついたら、その時はかなり期待できるよ、とも言っていました。
ましてやアマチュアの我々は、さらにきちんとティーチングプロに見てもらわないとだめだということに気が付くべきです。日々違うゴルフをしているんですから。
ラベル: 入門